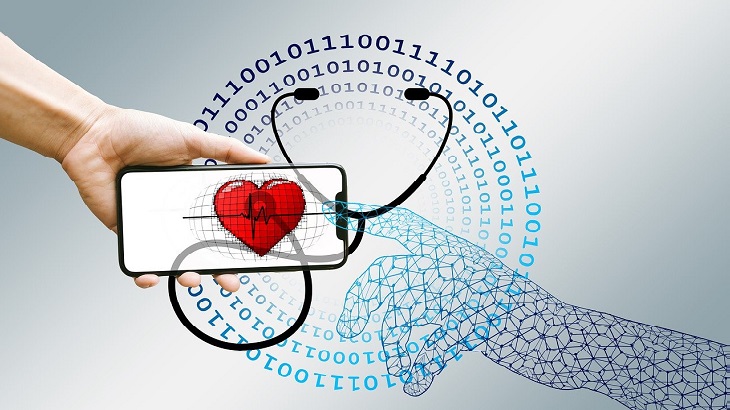医療現場がデジタル化する中で、スマートフォンやウェアラブルデバイスを用いたモバイルヘルスケアは、市民の健康管理を一変させるツールとして注目を集めています。日常生活で手軽に健康データを記録することで、疾患の早期発見ができるようになり、医療の効率化につながります。
このように、患者自身が積極的に健康を管理する新しい形が広がりつつある一方で、データセキュリティや高齢者への普及といった課題も浮き彫りになっています。本記事では、モバイルヘルスケアの現状や課題、そして導入事例を通じて、モバイルヘルスケアの可能性を解説します。
モバイルヘルスケアとは

モバイルヘルスケアの定義
モバイルヘルスケアとは、スマートフォンやウェアラブルデバイスなどのモバイル技術を活用し、個人の健康を管理、促進する仕組みです。この技術は、日々の運動量、心拍数、睡眠パターンといった健康データを収集、分析するだけでなく、医療従事者と患者との間でデータを共有することで、診断や治療をサポートします。
従来の医療では、患者が医療機関に足を運ぶ必要がありましたが、モバイルヘルスケアにより、患者は自宅や日常生活の中で健康を管理することが可能になりました。さらに、リモート診療や健康モニタリングを実現することで、医療格差の是正にも寄与しています。モバイルヘルスケアは特に高齢化社会が進む中で重要性を増しており、今後さらに幅広い分野で応用が期待されています。
医療DXにおけるモバイルヘルスケアの位置づけ
医療DX(デジタルトランスフォーメーション)は、医療サービスの効率化、質の向上、患者中心のケアを実現することを目的としています。その中でモバイルヘルスケアは、DXを具体化する主要な要素の一つです。
モバイルヘルスケアは医療機関と患者をつなぐツールとして、リアルタイムな健康データの収集・共有を可能にします。また、これらのデータを活用したAI診断や遠隔モニタリングは、特に地域医療や慢性疾患管理において重要です。さらに、データ解析に基づく予防医療の強化も進められており、医療費削減や健康寿命の延伸といった社会的な課題の解決にも貢献しています。
モバイルヘルスケアの現状と課題

モバイルヘルスケアの現状
現在、モバイルヘルスケアは世界中で急速に普及しています。スマートフォンの普及率は多くの国で90%以上に達し、ウェアラブルデバイス市場も年々拡大しています。これらのデバイスを活用した健康管理アプリは、運動、栄養、睡眠、ストレス管理など多岐にわたり、利用者は自身の健康状態をリアルタイムで把握可能です。
また、医療機関でも電子カルテシステムやリモート診療プラットフォームの導入が進み、患者データをクラウド上で一元管理する動きが広がっています。これにより、診断の精度向上や医療従事者の業務効率化が期待されています。
主な課題
モバイルヘルスケアの普及には多くの可能性がある一方で、いくつかの課題も浮き彫りになっています。第一に、データセキュリティとプライバシー保護が挙げられます。個人の健康データは極めてセンシティブな情報であり、不正アクセスや漏洩のリスクを最小限に抑えることが重要です。
第二に、デバイス間の互換性やデータ形式の標準化が不十分なため、異なるプラットフォーム間でのスムーズなデータ共有が課題となっています。特にデバイスの操作に抵抗感のある市民にとっては、利用の敷居が高いという問題も存在します。また、医療従事者側では、新しい技術に適応するための教育や訓練が必要であり、導入初期には負担が増えることも考慮しなければなりません。
医療DX化による解決方法

データの一元化と連携強化
医療DXの進展により、データの一元化と連携が急速に進んでいます。例えば、電子カルテシステムとクラウドプラットフォームを連携させることで、患者データの共有が容易になり、診断の精度向上や医療の効率化が期待できます。さらに、AI技術を活用することで、大量の健康データを分析し、病気の予兆や最適な治療法を提案する仕組みも導入され始めています。
プライバシー保護の強化
モバイルヘルスケアの普及には、データセキュリティの強化が欠かせません。具体的には、ブロックチェーン技術や高度な暗号化技術を用いたデータ管理が進められています。また、データ利用の透明性を確保するために利用者に対してデータ収集の目的や活用方法を明示する取り組みが増えています。
アクセシビリティ向上
モバイルヘルスケアの成功には、デバイスやサービスのアクセシビリティ向上が欠かせません。現在、多言語対応や高齢者向けの簡易操作モードを備えたアプリケーションの開発が進められています。また、地方や医療過疎地においては、スマートフォンさえあれば基本的な健康管理が行える仕組みが重要です。そのため、公共機関や地域医療機関が中心となり、デバイスの貸与や操作指導を行うプログラムも有用です。こうした取り組みは、デジタル格差を減少させ、誰もが平等にヘルスケアを受けられる環境づくりに貢献しています。
医療従事者のサポート
モバイルヘルスケアの普及にともない、医療従事者にとっての負担軽減も重要なテーマとなっています。AIを活用したチャットボットや診療支援システムは、患者からの問い合わせ対応や初期診断の一部を代替することで、医療従事者がより複雑なケースに集中できる環境を作ります。また、オンライン研修やトレーニングプログラムを通じて、新しい技術やツールの習得を支援する仕組みも整備されています。
モバイルヘルスケアの導入事例
Welby(ウェルビー)マイカルテ

Welbyマイカルテは、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの自己管理・医療機関との情報共有ができるアプリです。このアプリを利用すると血圧・血糖値・体重などの測定値や毎日の食事・運動・睡眠の記録をかんたんに蓄積できます。加えて、測定時のデータを自動的にアプリに記録でき、収集されたデータは医師や家族と共有可能で、健康管理や生活習慣の改善・治療に役立ちます。
このアプリを導入した国分寺さくらクリニックは、4名の専門医が各々外来を行う、まちのホームクリニックです。当クリニックでは、生活習慣病の患者に対して管理栄養士による食事指導を行っており、日々の生活習慣の記録および管理栄養士への報告ツールとしてWelbyマイカルテを導入しています。このアプリを使うと、患者の日々の習慣や食事の写真、数値の目標の達成状況がわかるため、患者の治療への意欲向上につながります。また、食事の写真を確認すると患者の実体験が分かり、今まで面談や紙の記録で分からなかった食事の量が可視化され、より具体的なアドバイスが可能になります。
MeDaCa(メディカルデータカード)アプリ

MeDaCaは、検査データ、おくすり情報、レントゲン写真、健康診断書といった、身の回りにある医療情報をかんたんに自分のスマートフォンから収納・閲覧できるアプリです。日々の健康管理のほか、病院とのコミュニケーションツールとしても活用できます。医療機関向けにはMeDaCa PROが用意され、臨床検査会社とのシステム連携により、デジタル処理した一般検体検査を患者へ直接渡すサービスも可能となります。
慶應義塾大学病院では、MeDaCaアプリを用いて、血液検査や尿検査などの検査結果や薬情報のデジタル提供サービスを開始しました。血液検査や尿検査などの検体検査や薬情報は、通常、医療機関から患者に対して紙に出力して提供されます。しかしMeDaCaの仕組みと慶應義塾大学病院の電子カルテを連携させることで、患者はスマートフォンのアプリで各種検査結果や薬の情報を電子データとして受け取ることができるようになりました。これにより、患者自身で各種データを受け取ったり、スマートフォンの画面上で待合への呼び出しを受けたりすることができます。待合室で待つ必要がなくなるため、病院での待ち時間の有効活用が可能になります。
HELPO(へルポ)
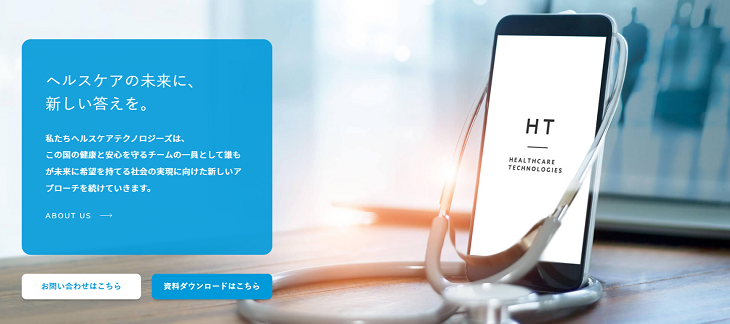
ヘルスケアテクノロジーズ株式会社が提供するHELPOは、体調が悪くなり始めたときや、ちょっとした身体の不安を医師・看護師・薬剤師の医療専門チームに24時間365日気軽に相談できるヘルスケアアプリです。HELPOを使うことで、ささいな体調不良や身体に関する不安を、いつでも医療専門チームにオンラインで相談できます。
このアプリを導入した静岡県藤枝市が設置する健康相談窓口は、平日日中のみ、かつ庁舎窓口のみの開設のため、対応件数や時間が限られており、市民の潜在的な健康課題を拾い切れていない課題がありました。そこでまずは実証実験として、市政相談窓口の時間外・非対面型の健康医療相談が受け入れられるかを検証し、市民のニーズを確認した後、HELPOを本導入しました。本アプリを導入した結果、従来の健康相談窓口で対応できなかった夜間や早朝における市民の不安解消につながり、これまで把握できていなかった潜在的な健康相談ニーズを確認できるようになりました。さらに、夜間休日当番医情報をHELPOの相談チャット上でユーザーへ連携することで、効率的な受診体制を実現しました。
ユビーAI問診

ヘルステック事業を展開するUbie(ユビー)株式会社は、AI搭載のWeb問診システム、ユビーAI問診を提供しています。AIが患者への質問を自動で生成するだけでなく、患者の入力内容を医師の言葉に翻訳します。問診の結果は電子カルテに自動で登録されるため、医師のカルテ記入の負担を大幅に減らすことが可能です。また、スマートフォンなどを使えば自宅でも問診が可能なため、患者の待ち時間削減にもつながります。
本サービスを導入した日本赤十字社 石巻赤十字病院の救急外来では、夜間対応が多いうえに医師事務作業補助者の配置も難しく、当初は患者や家族を待たせたり、時々お薬手帳を返し忘れたりという問題がありました。しかしユビーAI問診の導入によって、医師、看護師ともに、全体で約44時間の作業時間を短縮できました。現在は、看護師が直接患者に予診をとっていた時間や、医師のカルテ記入などの手間が削減され、医師、看護師ともに1回の診察で約3分ずつ作業時間の短縮ができるようになっています。さらに、医師たちの間で「面倒な記入作業などが減って楽になった」という意見が多く、時間的にも精神的にも余裕ができたことで、より丁寧な医療にあたる時間を捻出できるようになりました。
モバイルヘルスケアの展望
予防医療へのさらなる活用可能性
モバイルヘルスケアは、予防医療の分野で特に高いポテンシャルを秘めています。日常的に健康データを記録することで、個人が自分の体調を把握しやすくなり、早期に異常を発見できる仕組みが整います。また、こうしたデータをAIが分析し、生活習慣改善のアドバイスをリアルタイムで提供するサービスも進化しています。これにより、病気を「治す」医療から「防ぐ」医療への転換が加速しています。
AI診断とモバイルデバイスの連携による精度向上
AI技術の進歩は、モバイルヘルスケアの精度向上に大きく寄与しています。AIは膨大なデータを学習し、疾患の予兆や異常パターンを高精度で検出することが可能です。さらに、画像認識技術を活用して疾患を診断するアプリも開発されており、これらは専門医が不足している地域での診断をサポートします。こうした技術は、診療の精度向上だけでなく、医療へのアクセス改善にも寄与しています。
法制度や技術基準の整備に向けた動向
モバイルヘルスケアの普及には、法制度や技術基準の整備が不可欠です。現状では、データの取り扱いやプライバシー保護に関する法律が国や地域によって異なり、グローバルにデータを活用する際の課題となっています。これに対応するため、国際的な規格の策定やデータ管理のガイドラインが議論されています。デバイスやアプリの品質を確保するための認証制度や規制の整備が進むことで、モバイルヘルスケアの信頼性と普及がさらに加速する見込みです。
医療DXの一歩に、予約システムRESERVA

医療現場におけるさまざまな業務を効率化するにあたって、誰でも手軽に始められるのが予約システムの導入です。予約システムの機能は予約管理にとどまらず、予約者情報の管理と蓄積、スタッフやリソースの調整に至るまで自動化する機能を持つシステムです。複数のツールやプラットフォームを切り替える手間は一切不要で、これにより、クリニックや医療機関の業務プロセスがより効率的に進められるだけでなく、利用者にとってもわかりやすく使いやすい環境が提供されます。
現在は多数の予約システムが存在しますが、効率的な病院運営を実現するためには、実際に導入事例もあるRESERVA mdがおすすめです。RESERVAは、35万社が利用、700以上の医療機関が導入したという実績がある国内トップシェアクラスの予約システムです。予約受付をはじめ、機能は100種類を超えており、助産院・医療機関の業務プロセスがより効率的に進められます。初期費用は無料で、サポート窓口の充実やヘルプの利便性が高いため、予約システムの初導入となる病院やクリニック、薬局にもおすすめです。
まとめ
今回は、モバイルヘルスケアの意義や課題、ツールの事例を紹介しました。モバイルヘルスケアは、医療の質を向上させ、患者の生活の質を高める可能性を秘めている一方で、データセキュリティや技術基準の整備、アクセシビリティの向上といった課題にも直面しています。医療DXとモバイルヘルスケアの融合により、誰もがかんたんに健康管理ができるようになっています。患者中心の医療や予防医療の拡充に加え、医療従事者の負担軽減や医療格差の是正にも貢献するモバイルヘルスケアは、今後の健康寿命の延伸に寄与することが期待されます。
RESERVA mdでは、今後も医療DXに関する知見や事例を取り上げていきます。